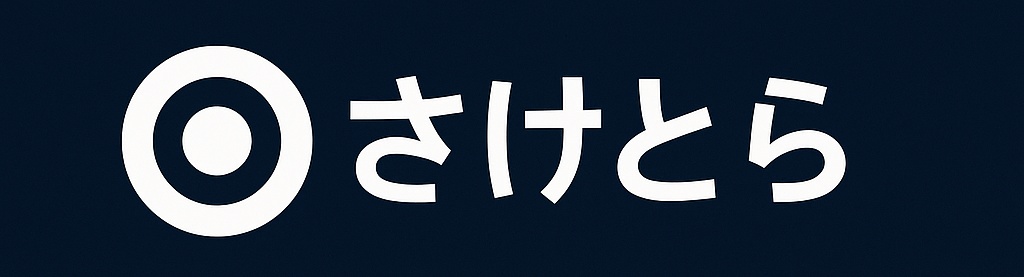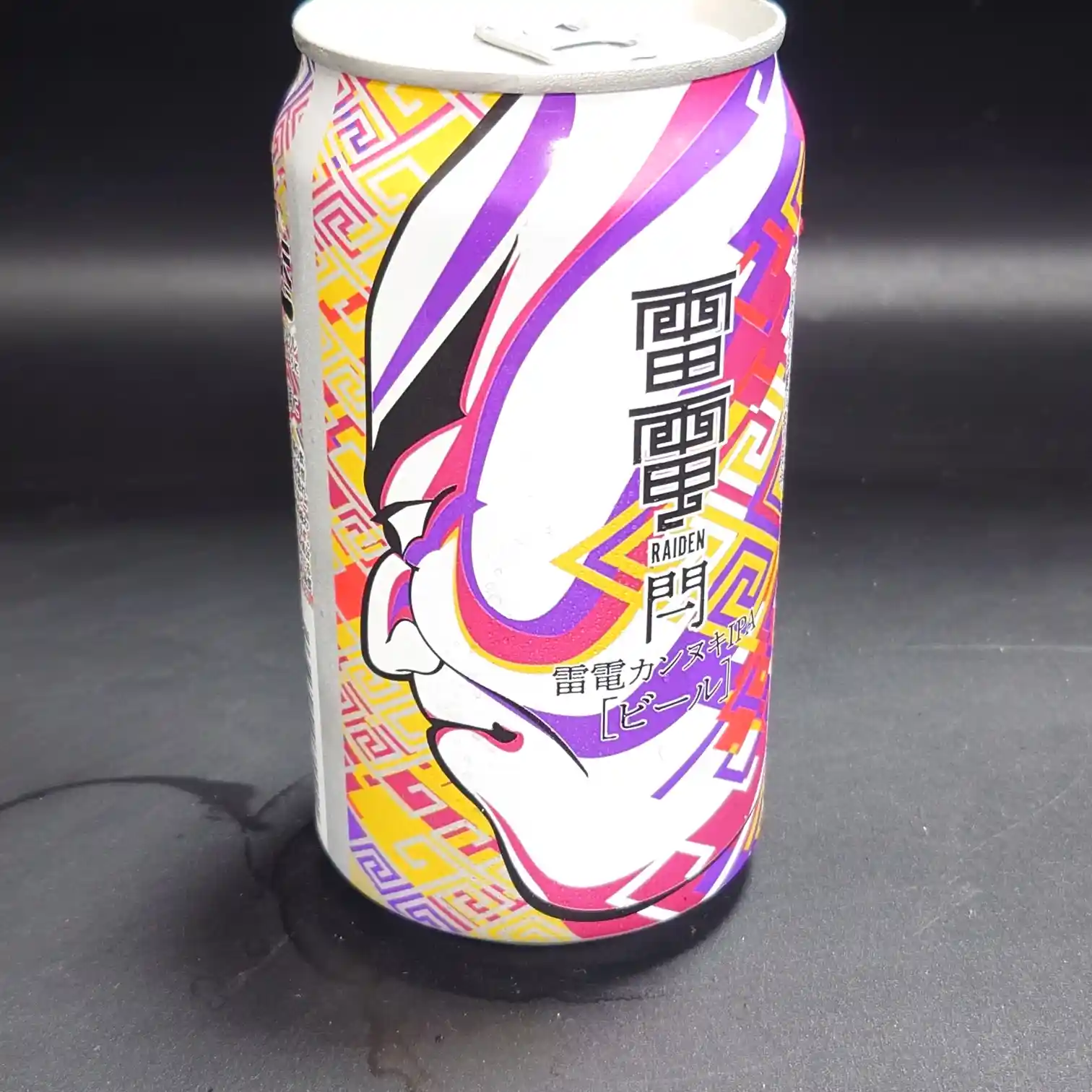から
「一滴でも危険?」
まで玉石混交。
結局“どれくらい”が現実的な
安全ラインなのか
私”モイ”が大好きなお酒と末永く付き合っていくため、
厚労省ガイドと最新研究を俯瞰して、迷いをスパッと断ち切ります。
適正飲酒量は
「1単位=純アルコール10g」
まずはこの“標準単位”を基点に考えましょう。
目安としては、男性は40g(4単位)、女性は20g(2単位)を超えると生活習慣病リスクが上がると言われます。
とは言え、10g、1単位ってあまりにも優等生では?と思い調べたところ、
男性:厚労省の「健康日本21」などでは、
1日平均で純アルコール20g程度(=2単位)
が適正飲酒量の目安とされています。
2単位とは、ビール換算500ml位といった感じです。
まぁわかる。そうだよね……。
まぁ納得………。
少し少ないけどね……。
女性:体格や代謝の違いから、男性の半分程度(=1単位前後/純アルコール10g)が目安とされています。
なるほど、女性は少ないのね……。
※妊娠中・授乳中はもちろん推奨されません。
【計算してみましょう】あなたの1杯は何グラム?
1. まず“純アルコール量”で考える(ガイドラインの芯)
純アルコール量の式:
容量(ml) × 度数(%) × 0.789 = g
📏 お酒の単位(標準単位)って?
管理をシンプルにするために、
標準単位=純アルコール10g
という単位を使います。
上の計算ツールや下の表もこの単位で考えると直感的。
- ビール缶350ml(5%)≒ 14g ≒ 1.4単位
- 日本酒 1合180ml(15%)≒ 22g ≒ 2.2単位
- ワイングラス150ml(12%)≒ 14g ≒ 1.4単位
- ウイスキー シングル30ml(40%)≒ 9.5g ≒ 約1単位
※“男性40g/女性20g以上でリスク上昇”目安は、それぞれおよそ4単位/2単位に相当。
🍺 よく飲む一杯=何グラム?(暗算リスト)
| 飲料 | 分量 | 概算(g) |
|---|---|---|
| ビール | ||
| ビール | 缶 350ml(5%) | 約 14g |
| ビール | 中瓶 500ml(5%) | 約 20g |
| 日本酒 | ||
| 日本酒 | 1合 180ml(15%) | 約 21〜22g |
| 日本酒 | 四合瓶 720ml(15%) | 約 85g |
| ワイン | ||
| ワイン | グラス 150ml(12%) | 約 14g |
| ワイン | ボトル 750ml(12%) | 約 71g |
| バーボン/テキーラ(40%) | ||
| ショット | シングル 30ml | 約 9.5g |
| ショット | ダブル 60ml | 約 19g |
| ハイボール | ||
| 缶 | 350ml(9%) | 約 25g |
| 店(グラス) | 約300ml(ベース30ml・40%) | 約 9.5g |
ガイドラインはあくまで「目安」。体調や気分で日々はブレます。
“1日”でなく“週”の合計で整えるのが現実的。
2. 胃腸の現実:飲み過ぎはすぐ炎症モード
慢性的にハイボリュームが続くと、
胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎、さらには膵炎リスク
まで波及。
粘膜の防御力が落ち、回復にも時間がかかります。
基本動作は2つ——
空腹で飲まない/同量の水(チェイサー・和らぎ水)
水を挟むと味や香りの再現性も上がります。
3. 脳(認知症)について:Jカーブ神話から“少ないほど良い”へ
近年の大規模解析では、
飲酒量が増えるほど認知症リスクが直線的に上昇
という報告が相次ぎます。
とくにメンデル無作為化(遺伝子を使った因果推定)では、従来の「少量は保護的」というJカーブは支持されにくい傾向。
結論はシンプル——
“ゼロか、なるべく少量”が脳にはベター。
※個別研究で強さは異なりますが、共通メッセージは「保護効果は期待しない」方向。
4. “楽しみながら守る”5つのルール
- 量を「グラム」で記録:アプリや手帳で見える化。
- 週に2日の休肝日:連続飲酒を断つ。
- 水は同量:1杯につき水1杯。脱水・悪酔い対策。
- 空腹NG+たんぱく質:胃壁を守り吸収をマイルドに。
- 睡眠×軽運動で整える:翌朝30分の散歩だけでもOK。習慣に。
香りと味を“保つ”飲み方ガイド
「空腹で飲まない」+「同量の水」
は健康だけでなくテイスティング精度でも必須。
現場の定番テク+生理学の知見をまとめますのでうまく取り入れましょう。
1)空腹NGの理由(テイスティング的にも損)
- 吸収が一気に進む
…胃が空だとアルコール吸収が早まり、鼻・舌の感度が鈍りやすい
ナッツ・チーズ・全粒パンなどを先に。 - 胃粘膜の保護
…軽食→水→一杯の順で、刺激を緩和して感覚を均一化
2)同量の水を挟む理由(香り・味が“戻る”)
- 嗅覚のリセット
…嗅覚は同じ香りに十数秒〜数十秒で順応
無香の水をひと口→鼻で2〜3呼吸で回復。 - 味覚の再調整
…口中をニュートラルに戻し、次のグラスの甘辛・酸・苦のコントラストを明瞭に。 - 脱水予防…杯=水の同量が体調キープの近道。
3)テイスティングに習う“小ワザ”
- 水は常温〜やや冷(10〜15℃)の軟水。強炭酸・レモン水は味覚を歪めやすい。
- 無香の口直し…無塩クラッカー/食パンの耳。
甘味・スパイスは残香が強くNG。 - 順番設計…繊細→芳香→樽・熟成→甘口(清酒・ワイン)。ビールはラガー→エール→ホップ強→ロースト。
- “鼻休め”の間合い…1杯ごとに20〜30秒外気。人の嗅覚は20秒で香りに慣れてしまう特性があるので、鼻休めは30秒以上としてゆっくりと香りを楽しむ。
5. 飲んだ日の「回復ルーティン」:軽い運動が効く理由
“量を整える”のと同じくらい
翌日の整え方が大事。
軽い有酸素運動はリカバリーの相棒
です。
- 血流アップで回復体感◎:代謝の主役は肝臓ですが、循環が上がると倦怠感が抜けやすい。
- 自律神経の再調整:会話できるペースが◎。
- 睡眠の深さ改善:日中の軽い運動は入眠・深睡眠を後押し。
- ウォーキング20〜30分/スロージョグ15〜20分
- ヨガ・ストレッチ10分+外気浴
- 水分・電解質+朝食(たんぱく+炭水化物)をセットに
6. まとめ:今日の一杯を“未来に感謝される量”へ
ガイドは“線引き”。大切なのは体調と習慣作り。
①グラム換算 →
②週合計で俯瞰 →
③少ない方に寄せる
——この3ステップで、楽しみと健康は両立できます。
何事もストイックすぎると反動が来るもの。
現代のストレスを一瞬やわらげてくれるのもお酒
お酒は、
人と人の距離をふわっと縮める潤滑油
とも考えられます。
上手に使えば、食や人との時間を豊かにしてくれる相棒です。
記憶が飛ぶほど“浴びる”のではなく、
良いお酒+五感で“良い時間”を設計する——そんな大人の飲み方を推します。
※本記事は一般情報です。医療助言ではありません。20歳未満・妊娠中の飲酒は法律で禁止。持病・服薬中の方は専門家にご相談を。
※当サイトでは20歳未満の方の飲酒を推奨しておりません。お酒に関する情報は20歳以上の方を対象に掲載しています。ノンアルコール飲料の紹介も、20歳以上の方を対象としています。
酒語辞典 |mohilog
日本酒・ワイン・ビール・ウイスキーの用語を五十音で横断検索。